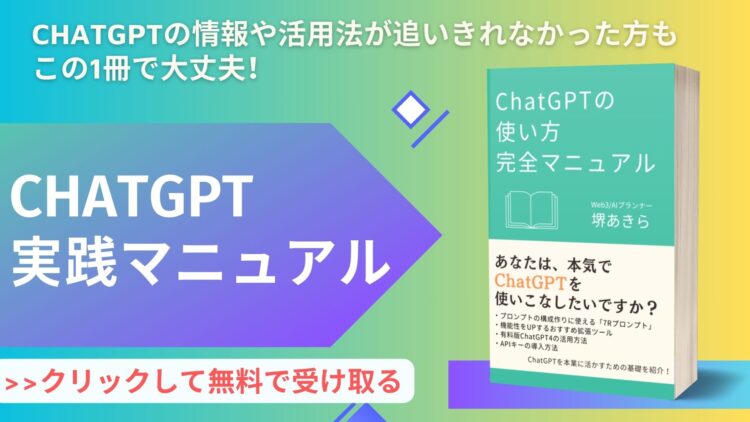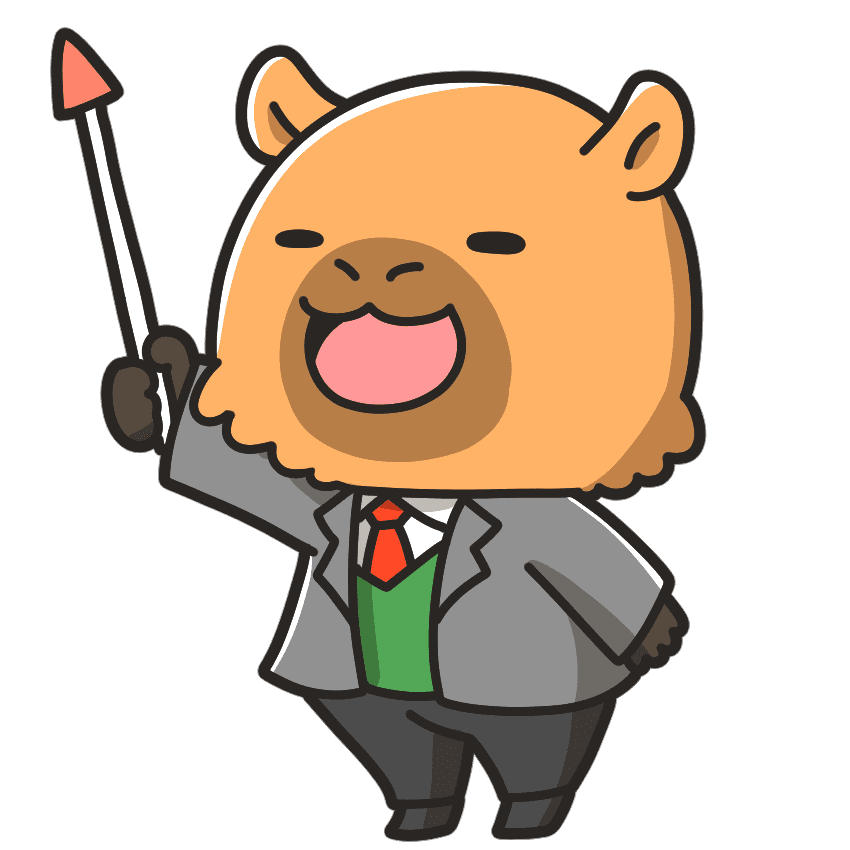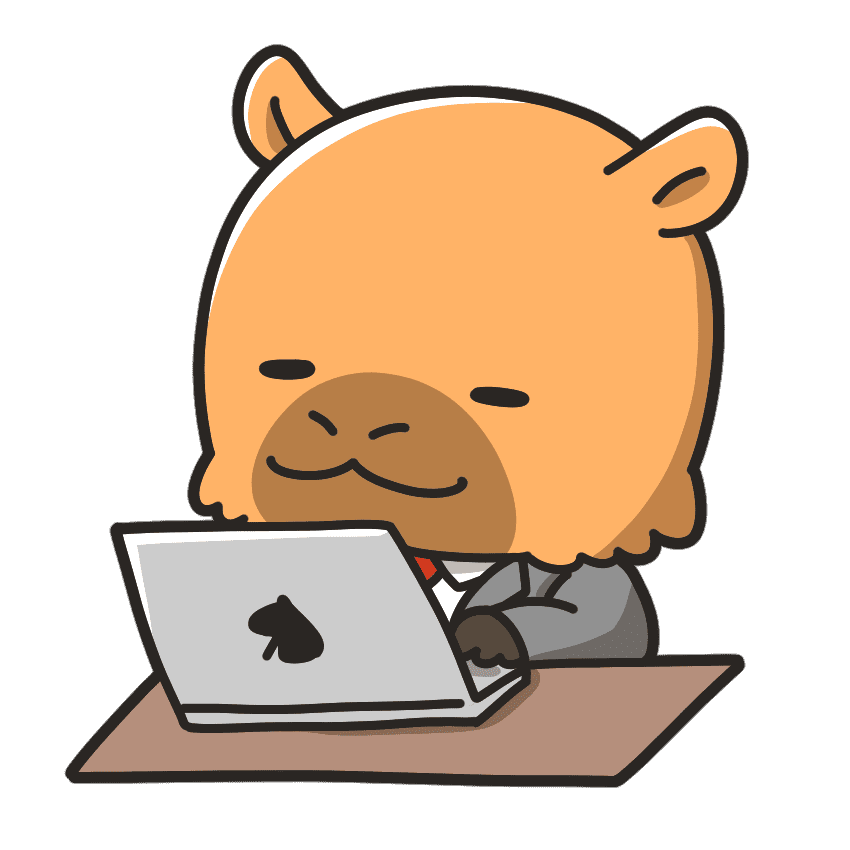「導入分の書き方とは?」「書く際に何か型はある?」などと疑問に思っていませんか?
記事やブログを書こうと思っても、最初の書き出し部分(導入文)の書き方が分からなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。
結論、導入文を書く際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 読者の悩みを提示する
- 読者の悩みに共感する
- 結論(解決策)を示す
- 信頼性や権威性を示す
- 本文を読むことのメリットを提示する
- わかりやすく簡潔にまとめる
上記の条件を満たしていれば、だれでも簡単に『先が読みたくなる導入文』が書けます。
本記事では、そんな導入分の書き方をブログを500記事以上書いてきたライター歴5年の私が、実例を示しながら詳しい書き方をまとめました。
導入文を書く際に使える型を一緒に紹介しているので、書き方に迷っているという方はぜひ参考にしてみてください。
導入文を書く目的:「本文を読んでもらうこと」

導入文とは「リード文」とも呼ばれ、「本文を読んでもらうこと」が目的です。
いざ読者がサイトを開いた時に、導入文に興味を持ってもらえないと文章全体を読まれることはありません。
逆に導入文で読者が知りたいことや読むメリット、記事の信頼性などが明記されていれば、文章全体を読んでくれる確率がグッと高くなります。
そのため、導入文は記事を書く際にもっとも注意して書かなくてはいけないポイントと言えるのです。
先が読みたくなる導入文の書き方を6STEPにて解説

先が読みたくなる導入文とは、読者に「この記事が読みたい!」と思わせる文章のことを意味します。
なので導入文では、読者に記事を読むことのメリットや解決策を提示していくことが大切です。
そんな導入文を書く際には、以下の6つの要素が満たされているかを確かめる必要があります。
- 読者の悩みを提示する
- 読者の悩みに共感する
- 結論(解決策)を示す
- 信頼性や権威性を示す
- 本文を読むことのメリットを提示する
- わかりやすく簡潔にまとめる
それぞれどういった書き方か、本記事の導入文を例にしながら見ていきましょう。
読者の悩みを提示する
まずは、読者の悩みを示していきましょう。
悩みを示すことで、読者が疑問に感じていることを具現化してあげることが大切です。
本記事の導入文を例にすると、以下の部分です。
「導入分の書き方とは?」「書く際に何か型はある?」などと疑問に思っていませんか?
読者の悩みをピンポイントで示せば、「この筆者は私の悩みを理解してくれている」と感じてくれ、記事を読んでくれる可能性が高くなります。
そのため、読者の検索意図を理解し、悩みに対して的確な回答を用意していくことが大切です。
読者の悩みに共感する
次に、読者の悩みに共感をしていきましょう。
何か悩みに対して共感をしてくれると、人は嬉しくなるもの。
そんな悩みを持っている人の心理を理解し、「あなたの悩み分かりますよ。」と示すことで、興味関心を引き出すことができます。
本記事の導入文を例にすると、以下の通りです。
記事やブログを書こうと思っても、最初の書き出し部分(導入文)の書き方が分からなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。
注意点として、共感するためには自身が悩みを理解していることを示さなくてはいけません。
同じ目線で話すことによって、読者から共感を得られます。
結論(解決策)を示す
導入文では、先に結論(解決策)を示すことも大切です。
本文に行く前に結論を簡潔にまとめることで、悩みを抱えている読者を安心させられます。
本記事の導入文を例にすると、以下の部分です。
結論、導入文を書く際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 読者の悩みを提示する
- 読者の悩みに共感する
- 結論(解決策)を示す
- 信頼性や権威性を示す
- 本文を読むことのメリットを提示する
- 分かりやすく簡潔にまとめる
上記の条件を満たしていれば、だれでも簡単に『先が読みたくなる導入文』が書けます。
1番の理想は、導入文で読者の悩みを解決してあげることです。
ただし、すべての解決策を導入文でまとめるのは困難なので、あくまで簡潔にまとめることを意識しましょう。
「より詳しい解決策を知りたい」と思った読者は、自然と本文を読んでくれるようになります。
信頼性や権威性を示す
導入文を書く際には、信頼性や権威性も示していきましょう。
読者に記事を読んでもらうためには、「この記事は信頼できる!」と感じてもらわなくてはいけません。
そんな時に、自身の権威性を示していけば、信頼されやすくなります。
例えば、本記事の導入文では、以下のように権威性を示しました。
本記事では、そんな導入分の書き方をブログを500記事以上書いてきたライター歴5年の私が、実例を示しながら詳しい書き方をまとめました。
いくら役立つノウハウを記事にまとめていても、「誰が言ったのか」で書いている記事が信頼されるかは大きく変化します。
信頼を獲得するためにも、自身が何者かを示していくことは非常に重要です。
本文を読むことのメリットを提示する
導入文の最後には、本文を読むことのメリットを提示しましょう。
本文を最後まで読むメリットを伝えることで、他の記事との差別化を図れます。
例えば、本記事の導入文を例にすると、以下の通りです。
導入文を書く際に使える型を一緒に紹介しているので、書き方に迷っているという方はぜひ参考にしてみてください。
読者に役立つノウハウをまとめるとなると、どの記事も似たりよったりとなります。
そんな時に、他の記事とは違う要素を加えてあげることで、読者にメリットを提示することが可能です。
わかりやすく簡潔にまとめる
導入文は、簡潔にわかりやすく書くようにしましょう。
先述したように、導入文を書く目的は「本文を読んでもらうこと」です。
長すぎると本文に行く前に離脱される可能性が高くなるので、短すぎず長すぎない導入文を意識しましょう。
伝えたい情報量を少なくしつつ、冗長表現を避けるなどして簡潔にまとめるクセをつけていくことが大切です。
【丸パクリOK】導入文を書く際に使える型を紹介
私はライター歴5年になりますが、導入文を書く際には毎回以下の型に従って書いています。
- ①読者の悩み
- ②共感文
- ③結論(解決策)
- ④本文の概要(権威性・信頼性の提示)
- ⑤記事を読むメリット
そして、実際に上記の型を本記事の導入文に当てはめていくと、以下の通りです。
①読者の悩み
→「導入分の書き方とは?」「書く際に何か型はある?」などと疑問に思っていませんか?②共感文
→記事やブログを書こうと思っても、最初の書き出し部分(導入文)の書き方が分からなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。③結論(解決策)
→結論、導入文を書く際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 読者の悩みを提示する
- 読者の悩みに共感する
- 結論(解決策)を示す
- 信頼性や権威性を示す
- 本文を読むことのメリットを提示する
- わかりやすく簡潔にまとめる
上記の条件を満たしていれば、だれでも簡単に『先が読みたくなる導入文』が書けます。
④本文の概要(権威性・信頼性の提示)
→本記事では、そんな導入分の書き方をブログを500記事以上書いてきたライター歴5年の私が、実例を示しながら詳しい書き方をまとめました。⑤記事を読むメリット
→導入文を書く際に使える型を一緒に紹介しているので、書き方に迷っているという方はぜひ参考にしてみてください。
先を読みたくなる導入文は、型さえあれば誰でも書けます。
あとは型にはめつつ、自分らしい言葉でオリジナリティを出して導入文をまとめていきましょう。
まとめ

ここまで導入文を書く目的や書き方、すぐにでも使える型を紹介していきました。
導入文を書く際のポイントを再度まとめると、以下の通りです。
- 読者の悩みを提示する
- 読者の悩みに共感する
- 結論(解決策)を示す
- 信頼性や権威性を示す
- 本文を読むことのメリットを提示する
- わかりやすく簡潔にまとめる
ブログ記事全体が読まれるかどうかは、『先が読みたくなる導入文』が書けるかで決まってきます。
ただし、本記事で紹介した型を利用すれば、誰でも簡単に導入文を書くことが可能です。
ぜひ本記事を参考にして、抵抗なく導入文が書けるようになることを祈っています。